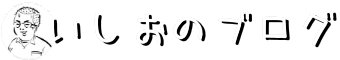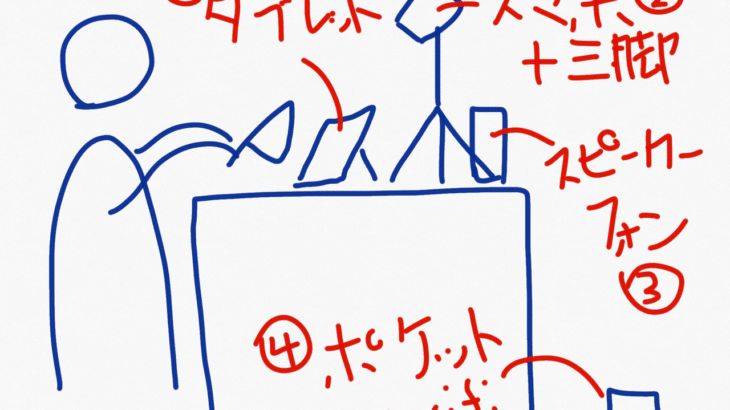今作っているサービスの価格設定や利益をどう上げるかに悩んでいる中、アマゾンで評価の高かった本「良い値決め 悪い値決め」を読んだのですが、考え方としてかなり勉強になりました!
なので、この本から学べることを紹介したいと思うのです。
僕らが住むような地方や田舎と呼ばれるところでは、特に経済的に疲弊しているところが多くあります。
ちょっとおおげさかもしれませんが、こんな状態を救えるのは「値決め」かもしれない、なんて思うくらいです。
「良い値決め 悪い値決め」で印象に残ったことを三行で
・値下げしがちな地方のお店必見!世の中には、利益が上がる上手な値下げと、利益が下がるヘタな値下げがあるよ!
・特に個人事業主は変動費の割合が高いので、値下げはつらい結果に!顧客への価値を意識して価格交渉を
・上手な価格設定のやり方としては「メンタルデコイ」と「フリープライシング」がすぐ使えそう
①地方の事業者がやりがちな「ヘタな値下げ」を回避するには

これは僕の住む沖縄のみならず、日本全体の問題だと思うのですが、極端に価格が安かったり、どんどん値下げしてしまったりするモノやサービスが多いように見えます。
特に田舎では、人付き合いもあるのと、「ぼったくりだ」「暴利だ」などと言われないようにするためにも、必要以上に値を下げがちです。
物価が安いのは消費者目線では良いことなのですが、その背景には働いている人がいて、その人がもらう賃金があります。
利益の少ないサービスばかりであれば、人に還元できるお金も少なくなってしまいますよね。
とてもシンプルですが、従業員に還元できる利益がないこと、これが低賃金問題の原因の一つです。
だから、低賃金問題を解決するための「値決め」は、地方や日本の未来がかかっている、といっても過言ではないように思うのです。
この本「良い値決め 悪い値決め」では、値下げには「良い値下げ」と「悪い値下げ」があると解説しています。
そして、マクドナルドの「100円バーガー」を例として紹介しています。
210円ハンバーガーの「良い値下げ」「悪い値下げ」

マクドナルドでは、当時210円で販売していたハンバーガーを、思い切って100円まで値下げしたところ、一個当たりの利益も増え、販売個数もなんと18倍になったそうです。
秘訣は一個あたり固定費の削減にあります。
大量に作り売るほど、一個当たりにかかる固定費が下がり、結果として利益が向上するのです。
これは良い値下げですよね。
しかしそれよりも注目したいのは、マクドナルドが100円ハンバーガーの販売前に行ったある実験です。
それは、「210円のハンバーガーを190円に下げる」というものでした。
20円、一個当たり10%の値下げは、その分多く売れないと利益が減ってしまいます。
しかしこの10%の値下げの結果、販売量は値下げ前と変わらず、利益のみ減ってしまう、という悲惨な結果に終わったのです。
ちょっとやそっとの値下げでは、販売量が増えない。
販売量が増えなければ、利益も上がらない。
だから、安易に値下げはしてはいけない。
この本ではそのように解説しています。
どのくらい販売量が増えれば良い値下げなのか?
この本、「良い値決め 悪い値決め」では、「どのくらいの値下げをしたら、どのくらい販売量を増やさなければいけないのか」についても紹介しています。
詳細は本書をご覧いただきたいのですが、一言でいうと「かなりしんどい」。
良かれと思って安易に割引や値下げをすると、販売量を何倍にもしなければいけない、つらい未来がまっているようです。
特に、生産量を大きく上げることの難しい地方の中小企業では、なかなか勝ち目の少ない選択肢といえるのではないでしょうか。
固定費が高めなビジネスでは値下げの勝ち目も
ただし、比較的固定費の割合が高いビジネス、例えば宿や航空会社などの設備投資の大きいビジネスに関しては、空室や空席をそのままにしておくよりも、少し割り引いてでも埋めた方が良さそうとも。
「1人来るのも2人来るのも手間は変わらない」といったビジネスでは、多く売ることで販売あたりの固定費が減りますので、比較的値下げの勝ち目があるかもしれません。
②地方の個人事業主が陥りがちな「貧乏暇なし状態」を回避するには
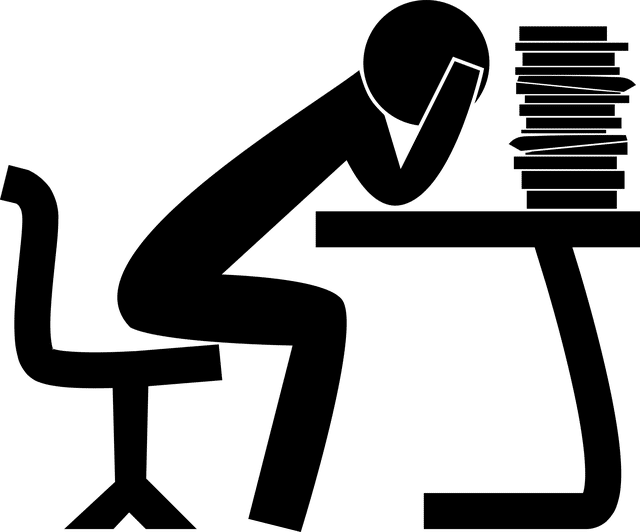
次は、複業ワーカー、個人事業主についての話に移っていきたいと思います。
最近は地方でも、インターネット回線を使って仕事をするリモートワーカーや、本業の合間にクラウドソーシングなどで案件を受注し仕事をする、複業ワーカーが増えてきているように見えます。
そして、そのような人たちは一定の収入を超えると個人事業主として登録し、営業活動を行っていくことになります。
で、僕も複業ワーカーとして島内外のいろんな案件をもらって生活してきたから痛感するのですが、特に地方の個人事業主は、気を付けないと、時間換算した単価が低い仕事を大量にこなす「貧乏暇なし状態」になりがちです。
例えば、クラウドワークスやランサーズなどで、ライター案件をいろいろ探してみてください。文字単価0.5円とか、0.3円のような案件がひしめいています。
僕も仕事が欲しいときに、文字単価0.5円の案件を受注したことがあったのですが、1日がかりで記事を書いても、1500円くらいの収入にしかならないことも(僕の筆の遅さのせいでもあるのですが)。
以前紹介した裏ワザでトータルの時間単価を上げることはできるのですが、このままでは複業としてもジリ貧ですよね。
https://i-shio.com/2019/02/22/slowhand1902/
変動費が高いビジネスは値下げするとつらい
この本では、特に「パソコン一つでできる」と言われるような、デザイナーはじめ、ライター、プログラマーのようなリモートワーカー・フリーランサーが、なぜ安易な値下げをしてはいけないかを、固定費・変動費の切り口で解説しています。
早い話、変動費が高い(=案件数と工数が比例するような)仕事は、安易に値下げするとそのまま利益が減るので、どんどん利益が減っていくのです。
当たり前の話に聞こえますが、やっている方としては陥りがちな落とし穴だと思います。
仕事をとらなければ、近い将来食いっぱぐれる。
それが個人事業主なのですから。
個人事業主が値下げを回避する交渉術
安易な値下げを回避する一つの手段として、現実的な方法をこの本「良い値決め 悪い値決め」では紹介しています。
早い話、価格交渉です。
顧客へ提供している価値を過不足なく見積り、価格を設定し、交渉する。
交渉にはこの本のみならず、いろんな先輩ライターやフリーランサーが言及していますので、いろいろ参考にしながらやっていくと良いかと思います。
ちなみにこの本「良い値決め 悪い値決め」でも交渉方法を紹介しています。
価格交渉の心理的負担を和らげてくれるような、ちょっとひねった、スパイスのきいたやり方です。
ぜひ読んでみて、その答えを探してみてください。
(言わんのかい)
③上手な値決め方法とは

この本「良い値決め 悪い値決め」では、良い値決めの方法を実例とともに紹介してくれています。
僕にとって印象的で、すぐに「これ、やろう!」と思ったのが次の2つ。
「フリープライシング」と「メンタルデコイ」です。
無料を組み合わせる「フリープライシング」
無料と有料の商品を組み合わせて販売する方法です。
無料より勝るお得感はない、といったことを本では解説しています。
確かに、「20%引き」とかするよりも、海外でよく見る「Buy 5,Get 1 free(5つ買うと1個無料)」とした方が心が動きますよね。
そして儲けも大きくなるようです。
高めの価格帯を用意する「メンタルデコイ」
松・竹・梅の3種類の価格帯を用意すると、人はどうしても真ん中の「竹」を好むそうです。
一番売りたい商品よりも高い価格帯の商品を用意する。
これが、メンタルデコイ(精神的なおとり)です。
メンタルデコイ自体も、売れたらラッキー。
終わりに
僕と同じように薄利で困っている人や、思うように売れない人、まずは値付けから考えてみるとよいかもしれません!
僕も今これを読んで、アウトドア体験プランを見直し中です!
一緒にやっていきましょうー!!!